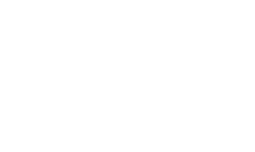今朝は軽く雪が積もりました。3月も下旬ですが北国ではまだまだ冬の名残が思い出したように一面を真っ白にしています。ここ数日〜1週間は雪だったり雨だったりと不安定な天気が続きそうです。気温も朝は氷点下になるようで。

目次
生後1ヶ月半だとまだ無理してお出掛けしなくて良い。

生後1ヶ月半の我が子はまだ外の環境に慣れ始めですから、こういう日には無理して出掛けずに家で暖かくしておくのが一番(赤ちゃんに限らず大人でも同じですけれど)。
特に雪が降る日は路面状況も含めて危険な場合もありますから、北国の冬の子育てって気を遣うものです。
我が子も2月上旬生まれだったので誕生後は「やっと外に出られる時期でもまだ寒いかもなぁ」とあれこれ考えていたものでした。
あとは家にいても暖かくし続ける必要がありますから、妊娠中〜出産後にかけてこの冬のシーズンは昼夜問わず暖房つけっぱなしだったり。
赤ちゃんの体内リズムと親の生活リズムの差がいつの間にか疲れとして蓄積されていたり。
その一方で私自身が最近喉風邪っぽくて声があまり出ない状態だったりします。育休をとってゆっくりと子育てに向かっているつもりなのですが、それまでとは違う生活リズムになって1ヶ月以上となると知らず知らずのうちに疲れがたまってきているのかもしれません。
こういう適応って男女差もあるんでしょうかね。何か本能的な仕組みとして「赤ちゃんのリズムに親も身体も自動的に調整される」ようになっていればなぁとか考えてしまったり(笑)。
人類の進化の過程で親側もできる限り負担が少ないようになっていても良さそうなものですよね。まぁその結果の今がベストなのかもしれませんけれど、それなら「育児ノイローゼ」みたいな言葉は生まれないはずだよなとか。
赤ちゃんと何ヶ月も身体的なつながりがあった母体の方がその適応度が高いのかもと思いつつ、ネット上では「夜中に赤ちゃんが泣いたので寝ぼけながらも起きてミルクをあげていると、旦那が隣で爆睡していてムカついた」みたいな話も。
ということは男女にかかわらず3時間毎のリズムには簡単には適応できるものではないのかな。出産後の夫婦の睡眠と覚醒のリズムがどう変化するのかを研究した論文があれば読んでみたいですね。
それで仮に親の体内リズムが赤ちゃんと同期するわけではないとすれば、特に夜中から朝にかけての「3時間サイクル(≒2時間睡眠+1時間育児)」は自分では大丈夫とは思っていても結構な身体的負担になっているのかも。
実際のところ何も問題なくスムーズに夜中のミルクやおむつ交換が済んだ場合にはまだ良いのですが、例えばうまくゲップが出なかったり、そのせいで中途半端な時間にゲボッてしまったり、それで着替えまでさせる必要がでてきたりとイレギュラーな対応が入ってくると大変ですよね。
まぁそのイレギュラーな事自体が慣れてくると「普通」になるわけですけれど。
時間や曜日感覚のズレをどう補正しながら社会性を保ち続けるか。
いずれ新生児〜乳児期の最初の方はどうしても家の中で親子だけの関わりの中で過ごす時間が多くなります。そうすると一般的な時間感覚だとか曜日感覚だとかとズレが出てくる場合もあって、その負担に自分たちでも気付きにくいという面もありそうです。
テレビのニュースやワイドショーを見るのが好きな人であれば気も紛れるかもしれませんが、我々の世代より下だとあまりテレビを見ないという人も多いでしょうし。うちの場合も最近テレビは(日中も夜も)ほとんど見ていなくてYouTubeなどを適当に流しっぱなし。
家族親戚や友人知人が訪問してくれる機会が多ければそれだけ社会性を保てますし息抜きだったり情報交換もできるので良いかもしれません。
SNSなどネット上のコミュニティでも良いとは思いますが、やはり実際に「家に来て母子の顔を見て話す」という場面は特別です。
あとは誰かが来ることで家を来客向けに片付ける動機付けにもなりますよね。それがプレッシャーだったりストレスになってしまうといけないのですが、子育てでバタバタしている中でも何かしらのタスクをこなすタイミングがあることは良いことだと感じています。
仕事ガッツリやって帰宅後に育児ガッツリやっている人がいるなら本当に凄い。
もし育休取らずに昼間は仕事をしているのであれば、1日の半分はそのサイクルで生活できる一方で帰宅後は育児生活となるのでまだリズムは整えやすいのかもしれません。
とか言いながら自分の前職での生活を振り返ってみるのですが、仕事ガッツリやって帰宅後に育児ガッツリやるってのはとんでもないスタミナ必要だよなと。
夜から朝にかけても対応するなら約2時間睡眠を細切れに取るわけですし。そうなると仕事から帰ってきてから沐浴だとかできることをささっとやって、朝までしっかり寝ないと体が持たないという父親がいてもおかしくないですよね。
ただこれ母親側が楽なのかって言えば決してそうではないのが問題なわけで。育休生活していてわかりましたが「ずっと家にいて育児していても大変なものは大変」です。これは「仕事していないから楽」ということではないと。
当たり前のことではあるんですが、このあたりは働き方や育児との関わり方を考えると父親母親それぞれで理解深める必要があるところだなと感じます。
私の場合は結果として育休生活できる働き方だったのでガッツリ育児に入っていますけれど、もし今もまだ勤め人のままだったら仕事から帰宅して朝まで育児という生活を続けていくことは体力的にかなり厳しいものになっていただろうなぁと想像したり。
まとめ
色々と書きましたが個人的には育児自体をストレスだとか疲れるとか感じることは全くありません。我が子の顔を見ていると何ともなくなるというのが親の心情です。新生児期から乳児期はもうずっと抱っこしていたいくらいで。
ただその一方で意識とは違う部分での疲れがたまってくるというのも確かだとは思います。これは父母どちらも。母親側は出産後は産褥期ということもあって意識的に身体を休ませようと考えやすいかと思いますけれど、父親側って身体を休ませることに無頓着な気がします。
特に普段は仕事をしている中で「育休」という「休み」を取ったという意識が先行しやすいので。育児されている親御さんであればわかると思いますが、育児って決して「休み」じゃないですよね。寧ろ24時間休みがない。だからこそ「育休の中でも自分たちの身体を休ませる」ことが大切になるわけです。
忙しい中でもうまく疲れを取っていきたいものですね。ではまた。