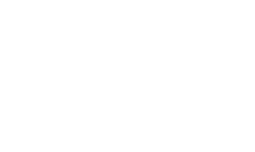目次
その商品のウリ、ちゃんと伝えられていますか。
商品開発やPR改善の場面で、例えばどのようなキャッチコピーでエンドユーザーに訴求するかという話になります。
そこで現状のウリ文句やパンフレットを見せてもらうと「本来の訴求ポイントってそこだっけ?」と感じることが少なくありません。生産者としての立場、製造者としての立場で「ここが重要!」と感じていることが、必ずしも相手に届くだけの差別になっていないということです。特にここではB to Cの場合についてです。
よくあるのが「安心、安全!」「手間暇かけて育てました」「こだわりの原料」「健康に良い」などなど。地方ほどこの傾向が強いようにも感じます。これらが訴求ポイントとなり難い理由を考えてみましょう。
ウリとして弱い訴求ポイントの例
「安心、安全!」
特に震災後の復興地域ではセンシティブな部分になっていることからも訴求ポイントとしてよく見かけるもの。生産地域イメージの改善を目的とした自治体単位のPR事業等であればこの点を出すのはまだ必要かもしれませんが、これは「マイナスイメージをフラットかプラスにする」という意味合いが強いので民間企業の商品ではこれだけで選ばれる基準にはなり得ません。
B to B商品などで安全性を担保するために根拠資料とともに入れておくのは構いませんが、B to Cでは訴求ポイントの第一にはならないということですね。
だってそもそも「安心安全じゃない商品を売っている人っています?」ってことです。いるかも知れませんが別に言わないでしょうし、安心安全と言っていない商品が危険心配ということではないですよね。敢えてそこを強調しすぎると反対に怪しまれるかもしれません。
「手間暇かけて育てました」「こだわりの原材料」
第一次産業だったり六次産業化開発商品だったりで見られます。産直レベルであれば「手間暇かけて育てました」でも構いませんが、これだけでは基本的には差別化のポイントにはなりません。加工品における「こだわりの原材料」も同様で、明らかなブランド野菜などを使用している場合であれば構いませんが根拠が薄いものだと響きにくいものです。
これらも安心安全と同じでそもそも「手間暇かけないで育ててる商品ってあります?」「原材料にこだわっていませんって全面に出している商品ってあります?」ってことです。つまりここが訴求ポイントになると考えるのであれば、「他の商品がこの部分をないがしろにしている(はずだ)と考えている」ということです。実際はそんなことありませんよね。
「健康に良い」
首都圏ではそれほど見られなくなってきているはずですが、地方ではまだまだ見られます。これは根本的な問題として「優良誤認」につながる表示はNGという部分につながります。根拠がはっきりしないものを効用として出していけないということです。
一応消費者庁のサイトを貼っておきます。
リンク先の表示関連の基準については目を通してみることをおすすめします。
法的に禁止されていないラインもありますが、そもそも敢えてそこを出していく必要はありませんし、エンドユーザーも賢くなっているのでエビデンスの乏しい商品は選ばれにくいと考えた方がよいです。仮に成分分析などで一定の根拠あるデータがあるとしても、商品のウリを考えるには別のアプローチであるべきです。大手百貨店などではこれ系の表記があるものは取扱NGとなっている場合もあります。
本来のウリは意外と当たり前な部分にある
当たり前の中に答えがある
では商品のウリとして何を推せばよいのか。ここからがブランディングの考え方になっていくのですが、ここではひとつの基準として「当たり前を書き出してみる」ということをやってみましょう。
「当たり前」というのがどのようなことかというと、例えば「人参」を例にしてみましょうか。「人参」は全国どこでも採れますし差別化しにくいですよね。変換していくと以下のような流れになります。
【簡易ワーク】人参を売り込め。
・安心安全なにんじんです!
んー、普通!
さて、ここから生産者さんにとっての「当たり前」って何だろうかとヒアリングしていきます。
・農家としてはいつから続いているのでしょうか。
・その人参の種・苗はどのように手に入れていますか。
・季節的にはいつ頃が旬になるのでしょうか。
・この地域では一般的な流通時期とずれることもありますか。
・気候的な特徴ってあるんでしょうか。
・他の地域の人参と食べ比べてどう感じますか。
・おすすめの料理方法は何ですか。 などなど。
特に生産者さんの普段の生活に紐づくことや、にんじんを育てる際の農家としての当たり前の知識や、地域特性からノウハウとして形作られてきた技など、「消費者からは見えていないシーン」を引き出すとポイントが見えてくることが多いです。
ヒアリングの結果、例えば下記のような形に変換できました。
・農家として8代続く〇〇町の□□農園で育てた人参です。
(生産者側の歴史や土着の価値が物語性を持って品質を担保する)
・〇〇町で江戸時代から守られてきた種・苗で作り続けています。
(特別な品種ではなくても土地ならではのこだわりが続いてきた)
・県内で最も寒暖差が大きい土地で、丹精込めて育てました。
(丹精込めてのみだと普通だが、気候の厳しさがシーンを連想させる)
・採れたてを野菜スティックにして食べるのが、農家の贅沢。
(作った本人の食べ方が、新鮮さと味を証明している)
いかがでしょうか。作った側にとっては「当たり前」のことを書き出してみることで、実は他の人参には無いオリジナルの物語やシーンが見えてきます。これがウリです。
考え方は人参でも商品でもヒトでも何でも同じ。
今回は人参という例で簡易的に見てみましたが、加工品でもどんな商品でも考え方は同じです。ヒトとしてのスキルを売り込んだり考えたりするときも同じです。自分にとって特別だと考えていることって、本来は特別ではなかったからこそ目立って見えるように感じているだけなものです。
例えば、英語を勉強してある程度話せるようになって「英語話せるよ!」といった所で、元々話せる人からすれば「で?」ってなりますよね。もともと持っていなかったものを努力して手に入れたからこそアピールしたいのはわかりますが、特にビジネス的な視点からは強みにするには相当なレベルが求められます。ネイティブには敵いません。
一方で日本人にとって「日本語話せるよ!」は当たり前ですが、立ち位置を吟味すれば強みになり得るのです。少しだけ英語ができれば海外の小さな良い商品を堪能な日本で紹介することができますし、日本側に営業をかけることもできます。海外の生産者にしてみれば、日本語をどれだけ勉強してもネイティブのあなたには敵わないのです。
いずれも突き抜ければ別ですが、ある一定レベルまでの場合には「当たり前」を見直すことが答えを見つけることに繋がります。
まとめ
訴求ポイントを考えるための方法論は様々ありますが、今回は「当たり前」という視点から整理してみました。
あなたにとっての特別は「世の中にとっての当たり前」になりがち。
あなたのとっての当たり前が「世の中にとっての特別」になり得る。
商品開発、商品改善、PRなど、見直してみてください。