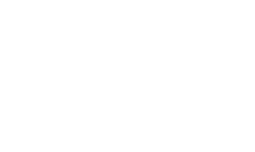今日は歴史的な日になりましたね。平成の次の新元号が「令和(れいわ)」と決まったことで、なんとなくボヤッとしていた改元のイメージがハッキリしたように感じます。日本最古の歌集である万葉集から意味と漢字を持ってきたということでこれも初めてのこと。
新元号「令和(れいわ)」は万葉集から。
時代が変わる雰囲気というものはやはりあるもので、世界的にも稀な「元号」というものが続いていることには意味があるよなと再認識したり。システム屋さんとか印刷業界などでは対応に追われてバタバタしているかもしれませんが、新たな需要が生まれるということでもありますから経済効果もかなりあるのでしょうね。
万葉集の元の歌があちこちで紹介されていましたので見てみましょうか。後半の「何以濾情」の「濾」という漢字についてはネット上で検索する限りだと「濾」「壚」「原文では手遍に盧」という表記が混在しているようなので原典実際に読んでみたいですね。
万葉集 巻五
梅花謌卅二首并序
天平二年正月十三日、萃于帥老之宅、申宴會也。于時、初春令月、氣淑風和、梅披鏡前之粉、蘭薫珮後之香。加以、曙嶺移雲、松掛羅而傾盖、夕岫結霧、鳥封穀而迷林。庭舞新蝶、空歸故鴈。於是盖天坐地、促膝飛觴。忘言一室之裏、開衿煙霞之外。淡然自放、快然自足。若非翰苑、何以濾情。詩紀落梅之篇。古今夫何異矣。宜賦園梅聊成短詠。梅花の歌三十二首、并せて序
天平二年正月十三日に、帥の老の宅に萃(あつ)まりて、宴會を申く。時、初春の令月(れいげつ)にして、氣淑(よ)く風和(やわら)ぎ、梅は鏡前の粉を披き、蘭は珮後(はいご)の香を薫(かをら)す。加以(しかのみにあらず)、曙の嶺に雲移り、松は羅(うすもの)を掛けて盖(きぬがさ)を傾け、夕の岫(くき)に霧結び、鳥は穀(うすもの)に封(こ)められて林に迷ふ。庭には新蝶(しんてふ)舞ひ、空には故鴈歸る。於是、天を盖(きにがさ)とし地を坐とし、膝を促け觴(さかずき)を飛ばす。言を一室の裏(うち)に忘れ、衿を煙霞の外に開く。淡然と自ら放(ほしきさま)にし、快然と自ら足る。若し翰苑(かんゑん)に非ずは、何を以ちて情を壚(の)べむ。詩に落梅の篇を紀(しる)す。古(いにしへ)と今とそれ何そ異ならむ。宜しく園の梅を賦(ふ)して聊(いささ)かに短詠を成すべし。
今後は万葉集関連の書籍とかまた結構出てきそうな気がしますね。大人になってからでもこういう歴史的な文献を改めて学ぶ機会が出てくるのも良いなと感じます。ずっと先のことになるでしょうけれど元号の漢字をどこから引っ張ってくるのかという考え方も今後も万葉集からという流れになるのかもしれません。
我が子の名前と誕生日が「令和」と関わる嬉しい偶然。
ちなみにちょっと驚いた偶然がありまして。2019年2月8日に産まれたばかりの我が子の名前、漢字の一部に「令」の字が入っているんですよ。部首だけなのですっかりそのままではないんですが。とはいえもちろん狙って付けられるわけもなく、親の思いを込めて選んだ漢字だったので何となく嬉しいですよね。次の時代につながるような気がして。
しかも上に挙げた「令和」の元になる万葉集の歌を見ていてさらに驚いたのが「天平二年正月十三日」の記述。天平二年というのは西暦730年。正月十三日というは旧暦で年によって正月の日付が変動します。ざっくり言うとある期間における「新月」の日が正月になるんですね。
それで「天平二年正月十三日」を新暦にしてみると「730年2月8日」。2月8日って我が子の誕生日ではないか!
1289年前の2月8日に詠まれた(生まれた)歌から付けられた元号が「令和」で、2月8日に産まれた我が子の名前にも一部「令」が入っているという。少なくとも「令」をこの万葉集の歌から狙って付けたならカッコ良いのですが偶然です。でも偶然だからこそ嬉しい。
自分の名前の由来だとか意味合いって自己肯定感と関わってくるものだと感じているので、この偶然も含めていつか我が子にはちゃんとしたストーリーとして伝えられればなと思います。
まとめ
ということで新元号の話題は山ほど出てくるでしょうけれど、非常に個人的な話題として新元号に対して我が子の名前と誕生日にちょっとした関係性が見つけられたということで嬉しい記録でした。まぁ世の中の「令」と「和」が付いている方は皆嬉しいネタにしているんだろうなと思いますが(笑)。
(2024/04/27 02:18:06時点 Amazon調べ-詳細)